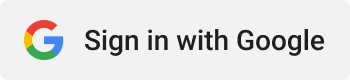ソムリエ試験 合格者の感想とアドバイス オリーブオイル大好きさん
第3章: 一次試験の勉強法1、それは日々、忘却と気力継続との闘い!
1. 1年目の失敗
いよいよ山崎先生の「ワイン受験.com」を受講し始めましたが、1年目は、定年退職直後ということもあり、孫のいる海外に長期間遊びに行ったりしていたこともあって勉強不十分で(言い訳ですが…)、結果、不合格でした。
しかし、1年目の大きな成果は、自分なりの、自分に一番合った山崎先生の「ワイン受験.com」の活用方法、受験勉強の方法、気力継続方法を見出したことです。
人生において、結局、無駄だったということは何一つありませんね(笑)。
2. 勉強の鉄則
そうして始まった2年目のチャレンジも、私のコーチは「ワイン受験.com」です。
その勉強方法の鉄則として、1年目の経験から、とにかく山崎先生の「ワイン受験.com」を使い倒そう、と決めました。
他の参考書、問題集等の教材には目もくれず(例外として、2冊だけ役に立った本がありますが、後ほど紹介します。)、迷わず、ただひたすら山崎先生の「ワイン受験.com」を最大限活用することに徹しました。
3. 具体的な勉強の進め方(その1)
まずは、「ワイン受験.comとは」を良く読んで理解し、勉強の進め方のイメージをしっかりと作りました。
加えて2年目では、山崎先生が渋谷にて無料で開催していただいたソムリエ、ワインエキスパート一次試験、二次試験のオリエンテーションを2月中旬に受講しました。このオリエンテーションの内容、資料は、二次試験本番まで、とても役に立ち本当に参加して良かったと思える経験でした。
また、先生に直接お会いでき、ネット上と何ら変わらない誠実な人柄にとても安心すると同時に、ワイン受験.comの動画同様にきちんと時間内に内容の濃いお話を分かりやすく説明してくださり、さらに信頼度が増しました。
このオリエンテーションの参加も、その後の勉強のモチベーションの維持、向上につながったと思います。参加可能な方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
4. 具体的な勉強の進め方(その2)
私の、基本的な進め方は、まず「ソムリエ一次試験対策講座2024」を一読し大まかにポイントを理解したうえで、「ソムリエ試験動画配信2024」を受講します。この動画を受講しながら、必ず先生が説明するポイントを自分が覚えやすいように整理してノートに書き留めます。動画の良いところは、自分の思うところで一時停止、見直しができるところです。
そして、先生がよく「教本のここは一読、二読することをおすすめします。」とおっしゃいますので、その部分はもちろん、一通り必ず教本は読み込んで、必要な箇所はノートに書き加えていきます。
5. 私のノートの使い方
このノートの使い方ですが、私が学生時代に習得したことは、「ノートは必ず見開き1ページとして使い、ノートはケチることなく余白を多めにとって(後々追加で書き込んだり、修正したりするためです。)なるべく綺麗な大きな文字で書くこと」でした。
追加の書き込みが多くなったり、汚くなってなんだかわかりにくくなったりしたら、頭の整理もかねて改めて書き直したりします。例えば、点数が伸び悩んだイタリアはノートごと、まとめ方も大きく変えて改めて整理しなおしました。
このノートを、寝る前に見直し、必ずベッドサイドに置いて寝ます。そして、次の朝目覚めたら、身体のストレッチをやる前に、このノートを再度見直します。さらに、一定の項目を受講しノートが出来上がったら、これをスマホで「写メ」します。
この「写メ」ですが、単に写真を撮るだけでなく、iPhoneでしたら、「メモ」機能の「書類をスキャン」で写真を撮ると、スマホが勝手に書類を認識し水平や余分なところをカットしてくれて、さらに単元ごとにファイルにまとめておくことができ大変便利です。
私は、この「写メ」を移動中、休憩中、病院の待合中など、時間があるときに何度も見直し、記憶の定着に最大限活用しました。これだと、電波の節約にもなります。
6. 問題集の活用
次に、一つの項目が終了したら、その都度「ソムリエ試験問題集2024」に取り組みます。最初にまだ十分理解し覚えていないときは、ノートやテキストを見ながら解きさらに理解を深めながら、問題集で新たに出てきた事項などをノートに書き加えていきます。 その日のうちに、自力で最低でも「B」判定が出るまで、できれば「A」判定となるまで何度も解きます。 また、外出中の移動時間、待ち時間や空いた時間には、スマホでこの問題集に取り組みました。この取り組みもとても役に立ちました。 私の場合は、この繰り返しでした。
大切なことは、先生が教えてくださる、重要な項目、国から勉強を順次進めていき、その重要な項目、国になるべくたくさんの時間を割いて、たくさんの問題を解くことが大切だと思います。ただし、後で焦らずに済むように、必ず進捗管理も併せて行うようにしてください。