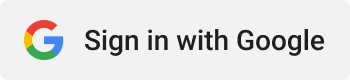ソムリエ試験 合格者の感想とアドバイス オリーブオイル大好きさん
第4章: 一次試験の勉強法2、それは皿回し方式!
7. 皿回し方式?
私のように60歳を超えると、中には依然として高い記憶力を保持している方もいらっしゃるとは思いますが、私の場合は、もともと記憶が苦手なこともあり、ホントに笑えるほど記憶力が落ちてきます。
私なりのその克服方法は「皿回し方式」です!
「皿回し」の芸は、一つ回したら、その一つにのみ気を取られることなく、ほかの複数の皿を落とすことなく見事に回していきますよね。
あの見事なやり方をマネして、とにかく、一度終えた項目は、あまり時間を空けずに、そしてあまり時間をかけずに手早く回す、そして、いろいろな項目をすでに終えた項目も含め時には同時に回す、特に弱点項目は多めに取り組み、問題を解くなり、ノートや教本を見直すなり、皿を落とすことなく「皿回し」を続け、記憶を定着させていくことを心がけました。
たとえ皿が割れても、笑えるほど忘れていてもめげずに、再び「皿回し」を続けていくことが大切だと思います。
8. 不得意な高いハードルから攻略せよ!
2年目の受験で最初に取り組むこととしたのは、1年目の受験の失敗経験で学んだ、私の最大のハードルの一つであるフランスの「ボルドー・メドック地区」の60個の格付けワイン、その他ボルドーのグラーヴ地区、サンテミリオン地区、ソーテルヌ・バルサック地区の格付けワイン、そして、フランスの「ブルゴーニュ」地方のグラン・クリュです。
この「ボルドー・メドック地区」の60個の格付けワインですが、私はノートの見開き1ページを使って、縦を等級別に、横を「ポイヤック」などのアペラシオン名として一つの表にまとめました。特に数の多いマルゴーの3級などは、覚えやすいよう独自の語呂合わせで、例えば「カントナック村」がきちんと区分できるような順番に並べて整理しました。もちろんこれも「写メ」に撮ります。
夜寝る前、朝起きてと何度となく見直し、さらに「ワイン受験.com」の「一日一問メルマガ」も活用しながら、子供がポケモンを唱えるように、繰り返し唱えながら覚えました。
先生も講義の中で、語呂合わせを教えてくださいます。一番のお気に入りは、イタリア・プーリア州の「プップカステル三兄弟」です(笑)。ネット上にも様々な語呂合わせなどが紹介されていますが、自分が覚えやすく、忘れにくい無理のない語呂合わせが良いのではないかと思います。
私にとって最大のハードルである分野を、とりあえずでも3月中には終えられたこと、そして徐々に得意な分野と言えるほどにまでなってくれたことは、その後の勉強のモチベーションの維持やリズムの継続に大きく貢献したと思っています。
このフランスのボルドー、ブルゴーニュ地区の成功体験は、その後の高いハードルであるイタリアのブドウ品種など他の分野でも、最後までホントに役に立っていて良かったなと思える経験です。
9. 問題集・模擬試験を解きまくれ!
先ほどもご紹介しましたが、「皿回し方式」でとにかく問題集を繰り返し解きながら、勉強を進めていくことがとても大切な合格への近道だと思います。
私の場合、それでも当初予定した問題数より実際には少なくて、最終的には1万問程度でした。もっと多く取り組むことができていれば、さらに点数・自信のUPにつながったものと思います。
さらに予定より少し取り組みが遅れたのですが、7月中旬をだいぶ過ぎてから「ワイン受験.com」の「ソムリエ模擬試験」に取り組みました。
この模擬試験で重要な箇所にもかかわらず、点が取れないところ、わからないところがあったら、必ず「問題集」に戻り解きなおして、復習・学習しなおしました。
結局、私の場合は、最後までなかなか安定してA判定をとることはできませんでしたが、先生がおっしゃる7月末までにC判定なら勝算ありとの言葉を信じ頑張った結果、8月に入るとほぼB判定、たまにA判定というところで受験に臨みました。
私は記憶力に限界を感じていましたから、最初から無理にA判定を狙わずに、例えば1問しか出ないような国などは、先生の動画を中心に最低限の時間しか割かず、主要な国や項目の問題で確実に点をとること、点を落とさないことに重点を置く作戦をとりました。
とにかく合格ラインに達することだけを目標として取り組みました。
10. 模擬試験、本番試験での独自解答ルール
考えてもわからない問題には時間をかけずあらかじめ決めておいた番号を選択すること、ある程度しぼれる問題は残る選択肢から解答すること、正解に迷いが生じた場合は最初に正解と思った選択肢を原則として変更しないこと、を私のルールと定め取り組みました。
このことは、CBT試験本番で、時間配分も含め、とても落ち着いて受験できたことにつながったと思います。
そうして、まさかの体調があまり良くない中で受験した1回目で、合格することができました。