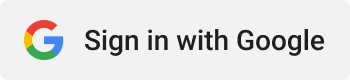ソムリエ試験 合格者の感想とアドバイス オリーブオイル大好きさん
第5章: 二次試験秘策? テイスティング用語を「見える化」
1. 一次試験突破直後に行ったこと
一次試験は、2回まで受験できますが、まさかの1回目の受験で合格してしまったので、これはうれしい誤算でした。飛び跳ねて喜びたい気持ちをグッと抑えて、妻の強い勧めに従い、早速、山崎先生の「ワイン受験.com」の「ソムリエ二次試験対策講座」に記載されている赤・白の基本3品種のワインを、同じものがなければそれに近いワインを買い求めることにしました。
私の場合、なるべくお金おかけ過ぎずに独学合格するぞ!と勝手に決めていたので、ワインスクールなどでも取り扱っている二次試験対策用のワインセットではなく、自ら直接買い求めることにしました。
それでも予算には限りがあるので、中でも特に重要と思われるもの、自身が未だ飲んだことがないものなどを中心に、ポルト酒やシェリー酒などを加えた20本程度を購入しました。
ワインは重いし、できればその日の夜から取り掛かりたいので、たまに行く都心のデパートのワインショップに車で向かい、店員さんと相談しながらワインを次々に選定していき、そこで揃えられないワインは、他のワインショップや後日、一部ネットで購入したりしました。
ワインショップの方のお話では、8月中旬頃から、ワインショップで私のような二次試験対策用のワインをまとめて注文する方が増えてくるらしいです。
一次試験突破の喜びにひたる間もなく、時間的に不安を抱えながらも速やかに二次試験に向け行動開始です。
2. テイスティング勉強の進め方
山崎先生の教えに従い、小瓶に移し替えて、計画を立ててテイスティングし、とにかくそのワインの品種・産地だけはなんとなくでもわかるように、少なくとも温暖か冷涼な地域のものか、赤だと濃いのか淡いのかなど、基本中の基本を再度、徹底して理解できるように日々、テイスティングを続けました。
(私の用意した小瓶は、後で妻が使えるように、ジャム用の瓶をたくさん買い求めました。この場合、グラスに移すときにこぼさないよう注意が必要です。)
一次試験突破に全力を集中するあまり、先生の教え通り、早くからの二次試験対策は心理的にも金銭的にも(笑)余裕がなく、一次試験合格後に始めたので、一発で二次試験を突破する自信は正直あまりありませんでした。当初は、一応、来年以降合格することも念頭に置き、その間テイスティングを楽しみながら深めていけばいいと、やや消極的な気持ちが優勢でしたが、徐々に今年で合格を決めたいと思う気持ちが強くなっていきました。
ということもあって9月中旬頃までは、いまいち二次試験対策にきちんと取り組めていない感じでしたが、その後、気合を入れなおし基本に戻って、山崎先生から直接受けたオリエンテーションと「ワイン受験.com」の「ソムリエ二次試験対策講座」をとにかく何度も読み返し、これを例の「ノート」にわかりやすくまとめはじめました。
次に「ワイン受験.com」にあるテイスティングの模範解答を参考に、とにかく基本をしっかりと固めるために、そのワインが温暖か冷涼か、濃いか淡いかなどの特性をしっかりととらえられるようになることに再度注力しなおしました。
さらに、そのワインの持つ特性ごとに、テイスティングの回答用紙の選択肢から、例えば温暖な地域の濃厚なワインなどの特性、方向性をしっかりつかみ、解答用紙全体がその方向性に合致した回答となるよう、温暖な選択肢と冷涼な選択肢が入り混じった、ちぐはぐな回答とならないよう特に気をつけました。
3. 二次試験対策のノート活用法
例えば、「ノート」に長く横線を引いて、両端に温暖、冷涼と書き、白ワインの「果実」の用語であれば、冷涼な方から順に「柑橘類」「青リンゴ」「リンゴ」の順に書き込み、反対側の温暖な方にはトロピカルな「パイナップル」「バナナ」などをすべて書き込みます。 これは、ワインテイスティング用語を「見える化」し、頭の中で瞬時にイメージしやすいようにするためです。
次に、テイスティングした白ワインが、その表のどこに位置するのかを判断します。軽めであれば冷涼な側の「柑橘類」あたりから複数選択します。たとえ自分が感じたとしても温暖側の「パイナップル」などは選択しないように注意します。
この表を頭の中にしっかりと定着させるように特訓しました。
この表にまとめるやり方は、他の「味わい」の「甘み」や「酸味」などの表現がどのあたりに該当するのかをしっかりと整理しておけばテイスティングの際、とても役立ちます。
さらに、この表は、「タンニン分」では横線の両端を「弱い」「強い」に変えて、弱い方から「サラサラとした」からはじめて、一方の強い方には「収斂性のある」という用語まですべて書き込めばOKです。他にも、アルコール度数の表現、余韻、苦みなど多くの項目で応用できます。
これ以外にも、表や図、絵などでまとめるととてもイメージしやすく、ブラインドテイスティングの際に、用語が結構スラスラ出てくるようになってきます。
以上は、あくまでも私の場合ですが、ホントに便利で役に立ちました。ぜひお試しください(秘策です(笑))。
4. 二次試験直前対策
二次試験直前には、空白のテイスティング解答用紙を相当数印刷しておいて、実際ワインは飲まずに(これだと朝から何度でも繰り返しできますよね。)、あらかじめ自分や家族が指定したワインの特性に合わせて、自分でノートにまとめたものに沿ってしっかりとイメージしながら、迷わず短時間で回答できるようになるまで繰り返し訓練しました。
二次試験は50分で5種類のお酒(ワイン4種類、その他1種類)をテイスティングするため、試験本番は、思った以上に時間が足りないとのことでしたので、とにかく「合格」を目標にそのような受験対策をとることとしました。
この時間が足りないとの情報はホントにそう感じました。
会場に時計はありませんし、腕時計も外しますので、試験官が時間を告げるやり方で時間を把握することとなります。したがって、この試験官が時間を告げるまで経過時間がわからないのですから、この特訓をやっていて良かったと思いました。あせらず落ち着いてテイスティングでき、念のため回答がちぐはぐなものとなっていないか確認する時間も十分取れました。
5. 二次試験を終えて
試験後の夕方にテイスティング銘柄発表がありますが、銘柄はワイン4種類中1種類しか合っておらず、後は収穫年、生産国が一部合っている程度で、その他の1種類も外してしまいました。このその他の1種類は、若い頃よく飲んだバーボンでしたし、きっとこれはボーナス問題だったはずだと思うと本当にショックで、正直落ちたなと思いました。
それでも合格できたのは、他の「外観・香り・味わい・評価」などである程度点数が取れたからということでしょうか。そこはわかりませんが…
先生の言う通り、品種等をきちんと正解できるのが一番ですが、私のように、品種を外しても、そのワインが温暖か冷涼かなど基本的な分析がきちんとできて、そのワインの特性、方向性を間違いなくとらえ、それをきちんと整理して回答できれば私のように合格する可能性もあるということではないかなぁと思っています。
もちろん皆さんは、はじめからそこを狙うのではなく、できるだけ品種等も正解できるようぜひ頑張っていただきたいと思います。きっとその方が間違いなく合格が確実となりますから。
少なくとも、最後まであきらめなければ合格の可能性は十分あるということだけはお伝えしておきたいです。
今後は、おかげさまで、なんとか合格できましたので、正しくテイスティングができるよう、これからゆっくりと楽しみながら、テイスティング技術をしっかりと身に着けていきたいと思っています。