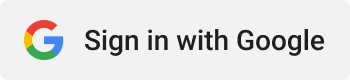受講生の声・ 仏文ワインさん
第4章: 勉強スタイルの確立
~ 教本の使い方~
教本は分厚いのでキンコーズでバラして使っていた昨年。持ち運びは楽でしたが、私は直接書き込むスタイルと見たいときに見たい気持ちが強かったので、2回目受験のときは敢えて分解せずに分厚い教本を持ち歩いていました(肩は死んだ)。
でもそのおかげで問題を解いていてわからない部分はすぐに復習できました。赤ワインは赤、白ワインは水色、ロゼはピンク、重要な文章は黄色マーカー、と色分けして書き込むスタイルで整理。地図も、先生がプリントに書いてくれている簡易な地図を余白に書き込み見直せるようにしていました。
~通学で学んだことはすぐに復習・習得をモットーに~
毎週の通学で学んだ部分は、必ず次までに復習し、大事な部分は教本に直接書き込みました。すぐにワイン受験.comの問題を解きます。とにかく解く。覚えられないポイントや地図は、ノートに書き込み叩き込むスタイル。苦手なところを国別にまとめていました。
~平日と週末の勉強バランス~
仕事が朝早く、帰宅は22時まわるのが基本で、とても平日は勉強時間を確保できませんでした。通勤時間とお昼休みに、苦手をまとめたノートと単語帳(チーズだけ単語帳に)、スマホでワイン受験.comの問題を解くというのを平日のルーティンに。
休日は、通学しない日は24時間利用可能なコワーキングスペースを借りて、朝から夜中までこもりました。平日にまとまった時間を確保できない分、休日は15時間以上勉強していました。ひたすら問題を解くスタイルです。国別・セクション別で、今日は日本を完璧にしよう、イタリアの20州を覚えよう、みたいな感じで、一日の目標を決めて取り組みました。
しかし、仕事との両立が結構きびしく、勉強できない時はできないので5月から勉強していたものの問題をこなす数にはムラがありました。本格的に1000問をこえて解きだしたのは7月中旬からでした。
そのせいか、国によってはD判定もザラで、くじけそうになりましたが、合格体験記を読んで気持ちを奮い立たせていました。
地図問は必ず一日一回以上解きました。ワイン概論、酒類概論、黒海付近の国々なんかも大事で、気が抜けませんでした。
捨てた国はスイス、イギリス、カナダです。スイスの土着品種、無理でした・・・最終的に、合計13,000問以上で、平均B判定。(2023年は6,000問弱、ほとんどC判定)