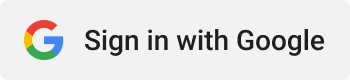ソムリエ試験 合格者の感想とアドバイス K/Mさん
第3章: 一次試験の勉強方法、毎日問題を解き、B判定取れるまで繰り返した
動画 → 教本を確認 → 問題集でアウトプット
私は、ワインエキスパート受験の申し込みが始まった3月のタイミングから勉強をスタートしました。申し込みをしてから10日ほどでソムリエ協会から教本が届いたので、それを使いながら学習を進めました。
勉強の進め方としては、まずワイン受験.comの試験対策講座と動画を視聴し、その都度教本を開きながら内容を確認していきました。重要だと感じた部分はノートにまとめ、その後はワイン受験.comの問題集に繰り返し取り組む形で進めました。そのため、一次試験の勉強で使用した教材は、ワイン受験.comと教本のみです。
動画のスライドはすべてノートに書き写し、そのノートに地図や図を書き足すなどして、できるだけ頭にしっかりと記憶できるよう工夫しました。また、蛍光ペンで色分けをしながら学習することで、視覚的に分かりやすく整理してきました。たとえば、白ワインは黄色、赤ワインはピンク(赤だと文字がつぶれてしまうため)、ロゼは緑色で色分けしました。この方法がとても効果的で、学習内容が整理されやすかったです。
少しずつですが、試験範囲を丁寧に進めていくことで、自信を持って一次試験に臨めました。
複数回答問題と地図問には特に注力した
ワイン概論、フランス、イタリアだけでも勉強範囲が非常に広く、正直なところ大変な部分もありました。しかし、この分野をしっかり押さえないと合格は難しいと思い、集中して取り組みました。特に、フランスのボルドーの格付けやブルゴーニュのグランクリュについては徹底的に覚えました。この部分が一次試験合格に大きく貢献したと思います。
理由としては、ボルドーやブルゴーニュに関する問題には複数回答を求められるものが出題されることがあるからです。これらの問題は配点が2点となるため、他の問題で失点しても、この複数回答問題を確実に取ることで合格点に近づけているのではないかという感触がありました。また、地図問題も同じく配点が2点となるため、ここを得点源にできると合格がぐっと近づくと考えました。
毎日問題を解く、B判定取れるまで繰り返す
一次試験はどうしても暗記が中心となりますが、試験範囲が広いため、暗記するべき内容も膨大です。そのため、勉強の途中で中だるみしやすい時期もありました。それでも、毎日少しでも試験問題に触れる習慣をつくることが大切だと思います。日々のルーティンを継続することで、一次試験突破への道が見えてくると感じました。
7月の初めまでに、頻出部分(ワイン概論、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、日本)について、動画を視聴しながら試験問題を解き、正解率をB判定以上になるまで繰り返しました。このサイクルを3回行い、基礎固めをしっかりと行いました。
7月の後半は、それ以外の範囲にも目を向け、全体を見渡しながら勉強を進めました。特に、ワイン受験.comにある「一次試験の出題傾向、配点、対策」というページが非常に役立ちました。このページには各範囲の出題割合が表でまとめられており、出題数が多い分野を中心に動画を視聴し、対策を練ることができました。
8月に入ったら模擬試験、正解率8割取れるまでやった
8月に入ってからは、ワイン受験.comの模擬試験に取り組みました。最初は記憶が曖昧になっていた部分も多く、残念ながら合格点には届きませんでした。しかし、点数が伸びなかった部分を分析して、自分の弱点(例えばドイツなど)を重点的に復習しました。そして、模擬試験を繰り返し受けながら弱点を克服していきました。
さらに、頻出部分だけでは合格ラインに届かないことにも気づき、マイナー分野からもしっかり点数を稼ぐ必要があると考えるようになりました。最終的に、模擬試験を7回繰り返す中で、正解率8割に届くまでトレーニングを積みました。
試験勉強は継続が重要だと実感しましたが、こうした段階的な取り組みが合格に向けた力になったと思います。
学習履歴は大変有用だった
ワイン受験.comでは、学習履歴を確認できる機能があり、自分の弱点や勉強が不足している部分を視覚的に把握することができます。勉強を進めている間はあまり気にしていませんでしたが、試験を終えて改めて確認してみると、総問題数は12,360問に達しており、正答率は79%でB判定でした。
ただし、ノートを見ながら回答した部分も含まれているため、実際の正答率は少し下振れすると思います。それでも、自分の努力の積み重ねを具体的に振り返ることができ、この記録が学習の進捗を客観的に見られる良い指標になったと感じています。