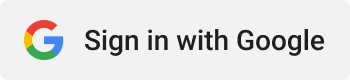ソムリエ試験 合格者の感想とアドバイス K/Mさん
第4章: 二次試験の勉強方法、対面の講座をいくつか受講した
二次試験のテイスティングはワインを飲んで、テイスティングコメントを行い、その後に品種、産地、ヴィンテージを絞っていく作業となります。ワインを生業としていない私には、どのようにテイスティングしていくか全くわかっていませんでした。
また、テイスティングは実技試験のようなもので、ワイン受験.comのwebページをみているだけでは合格は難しいと思い、以下のクラスを受講しました。
- 基礎からのワインテイスティング(基本編):山崎先生の対面講座
- ワインの資格を取ろう(二次試験対策講座):山崎先生の対面講座
- ヴィノテラスのオンライン講座
基礎からのワインテイスティング
「基礎からのワインテイスティング(基本編)」は、山崎先生が講師をしているNHKカルチャーの対面講座となります。全3回の講座で、1回目は白ワイン6種、2回目は赤ワイン6種、3回目は白ワイン3種+赤ワイン3種の計6種をブラインドテイスティングしていく講座となります。
ソムリエ試験・ワインエキスパート試験に出やすい基本的な品種のワインのブラインドとなります。講義の前半は、座学でそれぞれの品種の特徴や比較の講義となり、後半はいよいよテイスティングです。直前に学んだことですが、品種・産地を正解することは難しいということを改めて実感しました。
この講座は、5月25日(土)、7月27日(土)、9月28日(土)に開催されていたため、初回と2回目は一次試験の勉強中に開催されていたのは、一次試験の勉強の気分展開になり、二次試験へのイメージ作りにもなりました。
ワインの資格を取ろう(二次試験対策講座)
「ワインの資格を取ろう(二次試験対策講座)」も、山崎先生が講師をしているNHKカルチャーの対面講座となります。10月5日(土)に開催され、二次試験当日の二日前のまさに最終調整といった講座でした。
白ワイン6種、赤ワイン6種をテイスティングしていきました。試験直前ということで、テイスティングコメントの選択の仕方を確認したあとは、どんどんテイスティングしていきました。試験本番のようなタイトな時間制限だったため焦りながらテイスティングしていきました。
基本品種を総ざらいというワインだったため、それまで勉強していたことの成果もでて正答率も高く、二次試験への弾みにもなりました。
ヴィノテラスのオンライン講座
「ヴィノテラスのオンライン講座」は、ワイン受験.comとは異なるオンラインワインスクールとなります。知人の先輩ワインエキスパート合格者の方に、今後ワインを楽しんで飲んでいくのであればということでおススメされた講座です。毎回小瓶(100ml)につめられたワインが何本か送られてきて、それをテイスティングしていきます。
講義は、リアルタイムの配信を見ながらでもいいですし、予定があった場合は後日にその録画動画を見るのでも大丈夫です。初めのうちは、オープンブラインドテイスティング(その品種・産地が何かわかった状態でテイスティング)でそれぞれの品種・産地の特徴を学んでいきながら、ブラインドテイスティングにレベルがあがっていきます。
本番想定の講座では、実際に白ワイン2種、赤ワイン2種、その他のお酒2種(ワインエキスパートではその他のお酒は1種ですが、ソムリエ試験用に2種としているようです。多いほうが訓練にもなります)を、本番通りの試験時間50分でマークシートまで行うという訓練は、試験当日のシュミレーションになり、よかったと思っています。
ヴィノテラスのオンライン講座は費用としては、ある程度かかってしまうのですが、対面クラスが受講できない方にはおススメします。
自宅での小ビン詰め替え
上記のほかに自宅では、山崎先生のおススメのC1000タケダの小瓶にワインを入れ替えて、ワインの情報を書いたメモを裏にして輪ゴムで留めて、ブラインドテイスティングしていました。二次試験のコメントシートに慣れてきてからは、毎回コメントシートにテイスティングコメントを書いて対策していきました。
ブラインドしていたワインは、近所のイオンリカーで、二次試験対策用としてのワインをソムリエの店員さんと相談しながら選んで購入していました。
その他のお酒は対策せず
その他のお酒については、配点が低いわりに範囲が広いため対策はしませんでした。強いて言えば、近所のバーでコニャック、カルバドスを比較しながら飲んだくらいです。飲んだことのないお酒が出てきた場合は諦めて、山崎メソッドの選択肢を1にすると決めていました。